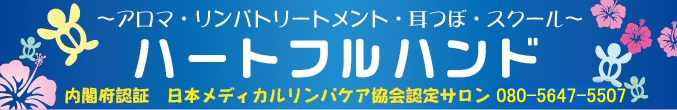オリジナル商品のご案内
埼玉県蔵元 日本酒と酒粕のうるおい石鹸「佐介 sake」
●精油のご紹介
「和の香り」を生み出した四種の精油について、その精油にまつわる文化やストーリーを主体にご紹介していきたいと思います。
参考文献とそこに記載された内容を箇条書きに記しました。
どれもすばらしい内容の文献となっておりますので、ご興味のある方はぜひ一読ください。
○オレンジ・スウィート
学名:Citrus sinensis
科名:ミカン科
抽出方法:圧搾法
〉効能
乾燥肌やくすみ、むくみのケアに効果的だと言われています。
〉精油の物語
★スコット・カニンガム『願いを叶える魔法のハーブ辞典』より
○オレンジは中国ではむかしから幸運や繁栄のシンボルだと考えられた。
。
中国を象徴する果物と言うと、桃のイメージが強かったので、少し意外な気もします。
オレンジの皮を煎じて飲むと、その後の酒酔いを防いでくれると信じられていたと言うので、漢方に近い存在だったのかもしれません。
また、オレンジの花から抽出した芳香蒸留酒(ハーブウォーター)には恋の特効薬の効果があるため、入浴時に使用するとその効果が得られるといいます。
「Love Fruit」の由来はこのような性格から来ているのかもしれません。
○ ゼラニウム
学名:Pelargonium graveolens
科目:フクロソウ科
抽出方法:水蒸気蒸留法
〉効能
肌の調子を整える効果があると言われています。
〉精油物語
★スコット・カニンガム『願いを叶える魔法のハーブ辞典』より
○庭で育てたり、切り花を窓のそばに飾ると魔除けの効果が得られる。
○蛇避けにもなり、
「ゼラニウム咲くところ?へびは寄りつかず」
という諺がある。
ローズと似た強い香りを放つので、それが魔除けや蛇避けのイメージとつながったと考えられます。
東欧ではヴァンパイア対策のニンニクが使われ、日本では鬼避けのため柊(サンマ付き)が使われ、いずれにせよ「悪いもの」を退けるために「強い香り」は不可欠です。
古今東西、悪いやつは鼻が敏感なのかもしれませんね。
○ラベンダー
学名:Labender angustifolia
科名:シソ科
抽出方法:水蒸気蒸留法
〉効能
幅広いスキンケアに効果的だと言われています。
〉精油物語
★スコット・カニンガム『願いを叶える魔法のハーブ辞典』より
○家のまわりにまいておくと円満な家庭を維持できる。
○なんども香りを嗅ぐことで長寿を導く。
○枕の下にラベンダーを置いて、就寝前に頭の中で願い事をする。その晩、願い事に関連する夢を見たら願いは叶うが、夢を見なかったり、願い事とは関係のない夢を見たら願いは叶わない。
★ニコラス・カルペパー『カルペパー ハーブ事典』より
○占星術では水星が支配している。
○外用内用とも、とても強い効果があると考えられていた様子。
○ラベンダーから抽出した油は"スパイクの油"と呼ばれ、刺激が強いため使用には注意が必要と書かれています。
つまり、精油のことでしょうか。
体表の病変にも内臓の異常にも数滴で充分で、単独ではなくブレンドして与えるべきだと言っているので、精油とキャリアオイルを合わせて使う現代のアロマテラピーと同じ方法を、この頃から始めていたのかもしれません。
★飯島都陽子『魔女の12ヵ月』より
○別名「紫色の妖精」
ラベンダーは、古代ギリシャ、ローマの時代からヨーロッパの人々の日常に利用されてきました。
イギリスではエリザベス一世、ビクトリア両女王に愛され、宮廷のさまざまな場面で登場したといいます。
○中世には悪魔祓いの効果があるとされ、ラベンダーの花束をドアや窓に吊るした。
ラベンダーもゼラニウム同様とても強い香りを持った存在ですから、悪いものを退ける力があると考えられたのかもしれません。
○ギリシア神話では「魔女の女王」と呼ばれるヘカテーに捧げる花。
○ラベンダーの語源はラテン語の「洗う」=「LavendulaやLavare」。
古代の人々はラベンダーの茂みの上で洗濯物を乾かし、香りを衣服や夜具に付けていた。
まるで平安時代の「薫衣香」のよう。
東西で文化の違いはあれど、「香り」を愛す人々の心はいつどこにいても同じなのかもしれません。
○「香りの庭の女王」とも呼ばれ、頭痛や筋肉痛、虫刺され、日焼け、湿疹、不眠に効果があると言われていたといいます。
○七月のラベンダーが咲く季節になると、街をラベンダー売りが歩き、虫除けにタンスなどに使われたラベンダーの交換の時期を知らせた。
中世の石畳の街を「紫色の妖精」とともに歩く商人と、その声に季節の移り変わりを知る人々。
想像するだけで、華やかな音楽が頭のなかに流れてゆく気がします。
★小野江理子『最新!アロマテラピーのすべてがわかる本』より
○ディオスコリデスが「汝の胸にある潤い」に効果があるとし、ヒルデガルトは「清純な性格を保つ」とした。
ディオスコリデスとは、ローマ皇帝ネロのもとで軍医として各地を回ったギリシアの医者兼植物学者。
ヒルデガルトは、ドイツ・ビンゲンの修道女で、「ドイツ本草学の祖」と呼ばれている人です。
キリスト教支配によって医学の発展を見せなかった中世ヨーロッパでしたが、修道院は古代ギリシアの本草書をもとに薬草園を作るなど、本草学発展の中心に位置していました。
なかでもヒルデガルトの功績は今日まで評価を得ていて、いくつかの著作も出版され、多くの人に愛されています。
ふたりのこと言葉は、「香り」が心にとって大切なんだよ、と言われているようで、なんともすてきな響きを感じます。
○ ローズマリー・シネオール
学名:Rosmarinus officinalis
学名:シソ科
抽出方法:水蒸気蒸留法
〉効能
毛穴の開きやたるみ、くすみに効果的だといわれています。
精神疲労を和らげる働きが期待できるとも。
〉精油物語
★スコット・カニンガム『願いを叶える魔法のハーブ辞典』より
○燃やすことで洗浄、浄化がもたらされ、いぶすことでネガティヴな場所が清められる。
○枕の下に置いて眠ると悪夢を見ず、あらゆる危害から守ってくれる。
○ローズマリーの花冠を頭にかぶると記憶力がよくなり、ローズマリーを炭で燃やし、その煙のにおいをかぐと博学になれる。
★小野江理子『最新!アロマテラピーのすべてがわかる本』より
○古代エジプトにおいて、ローズマリーは王の墓場に捧げる習慣があった。死者への敬意を表現するものだと考えられていたと言う。
○ギリシア、ローマでは「死」「記憶」「忠誠心」「学問」を象徴する植物であった。